厚生労働省が公的年金の長期見通しを試算する財政検証結果を公表した。
ホンマかいな?と思わせる内容である。
見通しが甘く楽観的過ぎると感じる厚生労働省の年金財政感覚!
経済成長と就業が進む標準的なケースで約30年後にモデル世帯の年金は実質的に2割近く目減りする。給付水準は50%を維持し、経済成長が見込めれば制度は持続可能と示した。
前提が楽観的過ぎる。
経済成長と就業が進むと思っているのだろうか?
経済成長が見込めると思っているのだろうか?
2015年(平成27年)の国勢調査の結果と総務省が発表している2050年の人口推移予測を並べてみたい。
| 2015年 | 2050年 | 増減 | |
| 総人口 | 1億2709万 4745 人 |
9515万人 | -25% |
| 0~14歳 (年少人口) |
1588万 6810人 |
821万人 | -48% |
| 15~64歳 (生産年齢人口) |
7628万 8736人 |
4930万人 | -35% |
| 65歳以上 (高齢人口) |
3346万 5441 人 |
3764万人 | +12% |
5年ごとに行われている国勢調査、1945年を除き右肩上がりであったが、2015年の調査で初めて日本の総人口は減少となったようだ。
そのまま日本の総人口は減少を続け、2050年には1億人を割り込むと思われている。
年少人口は約半数、生産年齢人口は-35%となるのに、どうやって経済成長をしていくのだろうか?
高齢者人口は思っていた以上に伸びていない。
高齢者人口は2020年までに急激に伸び、その後は緩やかな増加になると予想されている。
とは言え、総人口が減るので、高齢者割合は高くなる。
現役世代が高齢者を支える賦課制度となっている日本の公的年金、生産年齢人口と高齢者人口の割合を見れば2割減で済むはずがない。
(実際には公的年金は20歳以上から支払い義務があるが、15歳以上の数字の比較でもイメージ的には大差はないはずだ。)
ちょっと考えただけでも厚生労働省の算出は楽観的過ぎると感じてしまう。
人口動態に打ち勝つほどの運用利回りを出してくれるのだろうか?
そんな実力があるとは思えない。
こうした年金制度を信じて良いのだろうか?
日本の年金は100年安心とか制度は持続可能とか言っているが、そこには受給開始年齢を引き上げたり、受給額を引き下げたり、支払年金額を増やしていけばという前提があるはずだ。
仮に受給開始年齢が100歳となっても、制度は持続していると言い張るのかもしれない。
日本の公的年金、信じている人などほとんどいないと思うが、だからと言って自助努力している人はとても少ないように感じる。
☆ご質問やご相談等はこちらから。
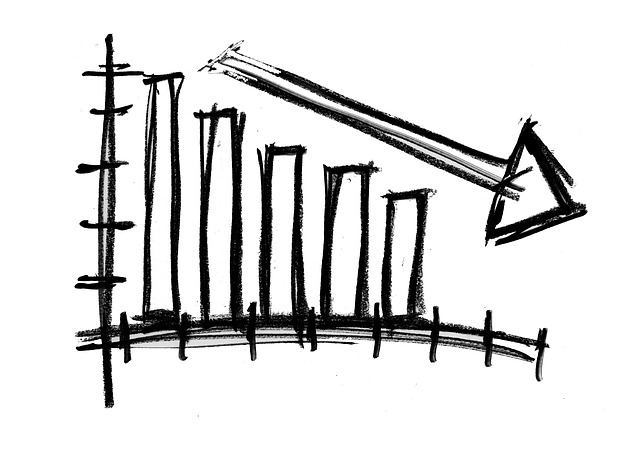

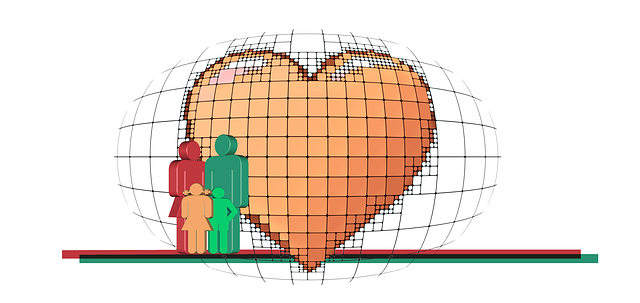
コメント