保険会社の利益は「死差損益」「費差損益」「利差損益」の三利源から決まってくる。
この三つの要素を分析していけば、日本の保険会社が利益が出ないのは当然と言える。
大事なお金をどこに預けるかをしっかりと考えるべきであり、将来の資産価値が増えるか減るかの重要な判断となってくる。
生命保険の三利源の分析!
生命保険会社の「死差損益」分析!
死差損益とは、実際に支払った保険金や給付金等に対して、予定死亡率に基づく保険金や給付金等の差額となる。
実際に亡くなってしまった人が予定死亡率よりも多ければ保険会社の利益は減ってしまう事になる。
これに関しては死亡予定率をどのように設定しているかによるので、日本と海外の差はそれほど無いと思われる。
ただし、保険会社によってはなるべく保険金を出さないようにして会社に利益を残そうとするところもあるようだ。
生命保険会社の「費差損益」分析!
費差損益とは、どれだけ事業費用が掛かっているかという事である。
日本の保険会社はとても多くの営業マンやセールスレディを抱えていて、更にはテレビ広告も頻繁に入れているので、海外と比較して多額のコストを吐き出している。
人件費や広告宣伝費が莫大な為、顧客に対して利益を提供し辛くなっている事が日本の保険会社が利益が出辛い要因の一つと言えるだろう。
生命保険会社の「利差損益」分析!
「利差損益」とは、運用による利益分である。
日本の保険会社は半強制的に低利回りな日本国債を購入させられている。
保険会社によっては運用の5割近くを日本国債で組成されているところもあり、運用で利益を出すのは困難な状況となっている。
海外の保険会社の場合は、当然ながらそうした縛りは全くなく、運用がし易い環境になっているのだ。
生命保険会社の三利源を分析してみれば、日本の保険会社が利益が出辛い事は明白だ。
「死差損益」は海外とそれほど差は生じないと思うが、「費差損益」と「利差損益」の格差が大きすぎる。
日本の保険会社は費用が嵩む割に運用力がなく、いわゆる費用対効果・コストパフォーマンスがとても悪い。
こうした状況の日本の保険会社を利用する理由は全く見当たらない。
海外、特にオフショア金融センターと呼ばれる地域は利回りが出易い環境になっていて、日本人の顧客を受け入れてくれるところもある。
一番利用勝手が良いのが香港と言えるが、香港では日本とは比較にならないほどの利回りとなっている保険商品もあり、結果としても実力差は明らかとなっている。
⇒ ご質問やご相談等はこちらから。
日本と海外の生命保険の比較!
生命保険の三利源から日本の生命保険が利回りが出難く、香港などの海外では利回りが出易いと説明をしてきた。
文章で説明しても分かり辛いかと思うが、海外の生命保険のシミュレーション結果を見ると、その差は明らかである。
以下リンクに幾つかのシミュレーション結果を載せているので、参考にしてもらえればと思う。

海外のいわゆる貯蓄型生命保険と呼ばれる商品は、利回り5%程度で複利運用されている。
日本にも貯蓄型生命保険と呼ばれる商品はあるが、死亡保険金は契約当初からほぼ変わる事は無く、早く死ななければ意味がないと揶揄されている。
貯蓄部分である解約返戻金も、満期近くになってようやく支払った保険料を解約返戻金が超える程度であり、貯蓄性はほとんどない。
こうした事から日本の保険会社の営業マンやFPは「保障と貯蓄は別のもの」と解説していたりする。
彼らからすれば、保障商品と貯蓄商品で2本契約してもらえれば有難い事だろう。
だが、実際には日本の保険会社が提供している保障特化商品も貯蓄特化商品も大した数字とはなっていない。
それは長生きリスクやインフレリスクにも対応できていないと言えるので、契約する意味がないのである。
一方、香港など海外の保険会社が提供する貯蓄型生命保険は、保障と貯蓄が両立できる。
死亡保険金は保険会社の運用(利差損益)により、契約後に右肩上がりで増えていく。
また、解約返戻金も同様に上昇していく。
支払った保険料を解約返戻金が超える損益分岐点を10年程度で迎え、その後はどんどん解約返戻金が増加していくシステムになっている。
保険証券を維持したまま一部引き出しもできるので、将来的には年金として活用する事も可能となっている。
こうした事から、海外の貯蓄型生命保険であれば、長生きリスクやインフレリスクにも対応できるのだ。
日本の生命保険は営業力は素晴らしいものがある。
テレビCMや営業マンの力によって保険会社の名前や商品名を知っていると言う人も多いかも知れないが、その中身はと言えば、お世辞にも褒められたものではない。
海外の保険商品や金融商品は保険業法や金融商品取引法によって、日本では営業活動ができないので、ほとんど知っている人はいない。
だからこそ、日本の保険会社は利回りの低い商品を販売できるのだが、世界の実情を知ると愕然としてしまうのではないだろうか?
⇒ ご質問やご相談等はこちらから。
海外の保険会社の商品はIFAと呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う!
日本と海外の保険格差、金融格差を知ると、海外の保険商品に興味を持つかもしれない。
海外の保険会社は直接クライアントを受け入れてはおらず、IFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを担当する事になっている。
だが、このIFAは日本国内には存在しない。
それは何故なら、金融商品取引法によって、日本国内に登録されていない金融商品の販売は禁止されているからだ。
だが、20世紀末の金融ビックバンにより、自らの意思で海外の金融商品を購入する事は合法化された。
その為、海外の金融商品を購入するには海外のIFA=正規代理店に直接連絡をしなければならない。
もう一つ付け加えておくと、海外の生命保険を契約するには内閣総理大臣の許可が必要と保険業法に書かれている事も知っておかなければならない。
実際に内閣総理大臣の許可を得て購入したと言う人は聞いた事がないのだが、この文言には更に理由が書かれていて、それは日本の生命保険会社を守る為となっている。
それだけ日本と海外の保険会社の実力差を危惧していると言うことだろう。
政府としては、国債の重要な売却先として、日本の保険会社を守らなければならないと言う大きな理由もあるはずだ。
海外のIFA=正規代理店に連絡すると聞いて躊躇してしまう人もいるかもしれない。
だが、日本人スタッフが在籍しているIFAもあるので、それほどビビる必要もない。
今はZoomなどのインターネットツールも発達しているので、自宅にいながら日本語でIFAと会話ができる。
日本人スタッフがいて、日本人の受け入れやサポート実績が豊富なIFAを選べば安心できるはずだ。
そうしたIFAに自身の予算や考え、家族構成などを伝えることにより、自身に合致した商品を案内してもらえる事だろう。
自分自身のシミュレーション結果を見れば、更に日本と海外の保険会社の実力差に驚く事だと思う。
「日本の常識は世界の非常識」「世界の常識は日本の非常識」を感じ取れるはずだ。
☆ご質問やご相談、IFA=正規代理店の選定でお悩みの方はこちらから。
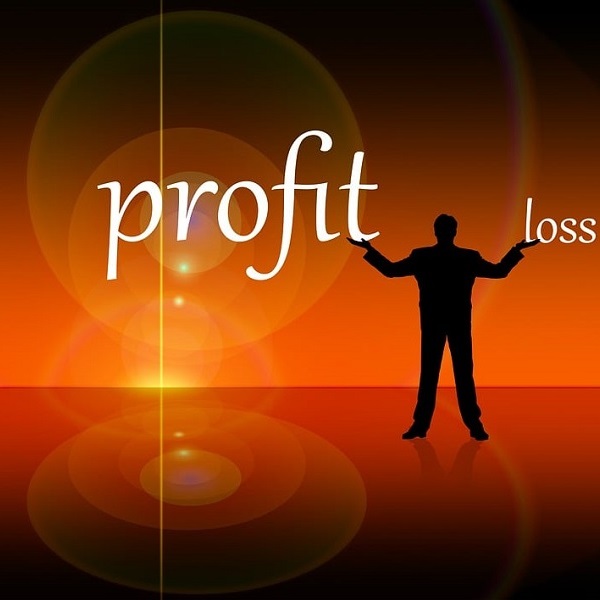


コメント