先日、10月17日は貯蓄の日だという事をコンテンツにした。
日本の銀行金利はどのような推移になっているのだろうか?と気になったので調べてみた!
郵便貯金1915年の金利は4.8%!?
銀行の金利推移を見るのはゆうちょが一番いいと思ったので、ゆうちょ(郵便貯金)の金利推移を調べてみた。
もちろん、銀行となったのは小泉政権以降なので、郵便貯金ーゆうちょ銀行での推移となる。
調べていたら、既にグラフ化している人がいたので、そちらを参考に色々と考えてみたい。
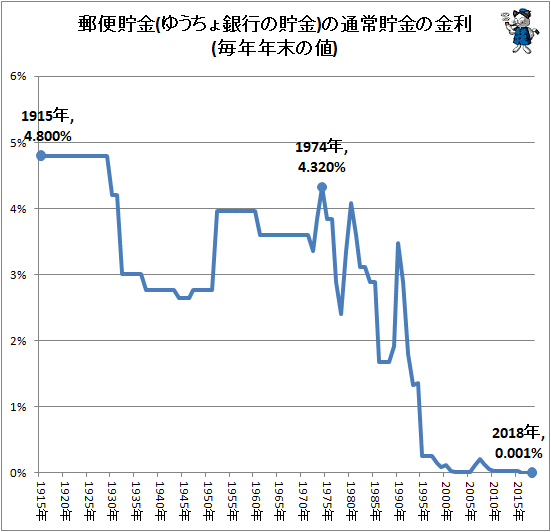
↑普通預金の金利
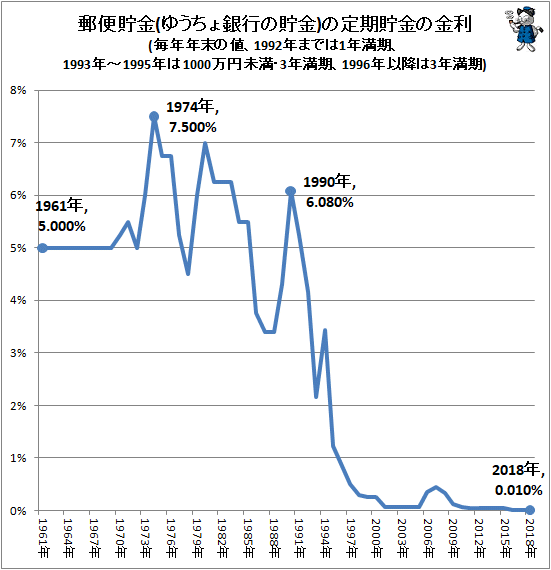
↑定期預金の金利
郵便貯金の普通預金のデータは100年以上前の1915年からある。
その当時で4.8%。
それが今ではほぼ0%。
バブル崩壊以降、約30年に亘って超低金利時代が続いている。
定期預金は1970年代に10%あったと見聞きしたことがあるが、違うのかもしれない。
それでも1974年には7.5%もの金利が付いている。
72の法則に従えば、9.6年で資産は倍になる計算だ。
| 72÷「年間利回り(年利)」=「資産が2倍になるまでの期間」 |
0.01%だと7200年かかって資産が倍になる。
紀元前5000年から定期預金を始めていたら資産が倍になる計算だ。
紀元前5000年とは古代エジプトの新石器時代で、日本の縄文時代前期である。
また、今から7,200年後の未来がどうなっているのかは誰にも想像できない。
さて、金利が高い国内の定期預金を探して定期預金を組めば良いかと言えばそうでもない。
そもそも金利は景気動向に比例しているので、金利が高いからと言って増えた資産の実質価値は変わっていない事になる。
また、金利自体も変動するので、今よりも高い金利となったら資産価値は目減りする。
そう考えると、平均的な景気=株価指数をベンチマークにして利回りを期待できる商品を契約するのがベストだ。
こうした考えに則って行われるのがオフショア積立投資なのだが、目先の数字だけに目を奪われて一喜一憂している人が多すぎると感じる。
長期投資だからこそ、長期的に見て世界の株価指数よりも利回りが大きくなればよく、どのファンドマネージャーもそうした考えでポートフォリオを組んでいるはずだ。
☆ご質問等はこちらから。
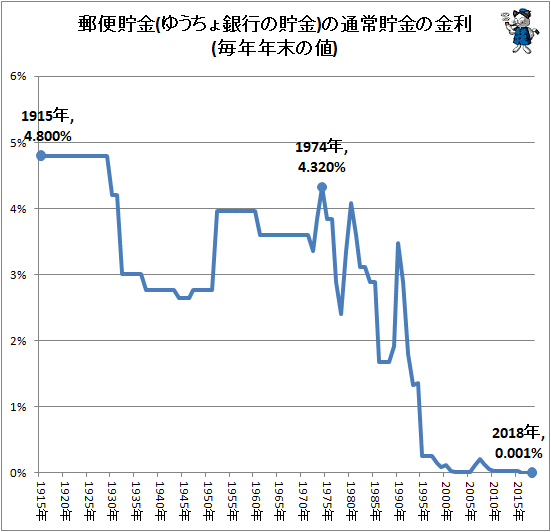


コメント