医療法人は公益財団となるので、業務形態に関わらず医療法で営利目的の病院や診療所、クリニックなど開設することができず、営利行為も禁止と医療法で定められている。
医療法人の設立時に定款を作成するが、そこで現金などの資産管理方法についても定義しているケースが多い。
縛りが多く悩みを抱えている医療法人の経営者が多いようだが、全ての資産運用を禁じている訳ではないようだ。
医療法人が行える資産運用方法とは?
医療法人の定款として、厚生労働省が作成したモデルを提供されている。
第3章 資産及び会計の第9条を見ると、以下のように書かれている。
資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信
託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。
”確実な”という単語が付いているが、この文章を真面目に考えると日本国内での運用はできなくなってくると思うのだが…
それは何故なら、日本国内の銀行や信託会社、国公債が確実とは言えないからだ。
資産運用によって病院経営に打撃を与えてはならないという考えに基づいての事だと思うが、では何ができるのだろうか?
株式投資などは確実なものとは言えず拒絶される可能性が高い。
不動産は医療法第42条で業務に支障を与えないように制限がされている。
不動産を所有として、医療機関や老人保健施設の為に不動産を所有する事は認められているが、収益物件の保有は認められていない。
生命保険は?と言えば、生命保険は特に制限されておらず加入が認められている。
変額年金は生命保険のカテゴリーとして扱われるようで、特に問題とならないようだ。
保険はあくまでリスクヘッジとして考えられていて、資産運用・投資目的ではないので営利目的に当たらずに規制されていない。
なので、医療法人としては生命保険商品を活用する事を検討すべきかなと思う。
ただし、厚生労働省が作成したモデルに書かれている”確実な”という文言に沿って考えれば、日本国内の保険会社が提供する保険商品は除外する必要があるのではなかろうか?
インフレーション・物価高に対応した商品を提供している日本の保険会社はほぼ見当たらない。
長期的に保有すればするほど、インフレに対応できずに資産価値が目減りする商品がほとんどだ。
海外に目を向ければ、保険会社の運用力によって資産価値が年々上昇していく商品が多い。
金融立国・オフショア金融センターと呼ばれる国や地域が提供している保険商品は日本とは比較にならないほどの利回りで運用されているのだ。
生命保険であれば、以下コンテンツのようなプランがある。

日本の生命保険とは比較にならないような利回りで運用されているので、経営者のもしもの時に対応できる。
日本の生命保険は、契約時に設定された死亡保険金が契約中にほぼ変わらないが、海外の生命保険商品は運用によって年々死亡保険金が大きくなっていく特徴がある。
また、貯蓄性もあるので、退職金代わりに活用する人もいたりする。
貯蓄額(解約返戻金)も死亡保険金と同じように運用によって年々上昇していくのだ。
日本の生命保険は早く死ななければ意味がないと揶揄されるが、海外の生命保険はその逆で、長生きすればするほど資産価値が高まっていく。
この商品の興味深いところは保険証券(死亡保険金)を担保にして、そこから切り崩しながら年金を受け取れるスキームがある点だ。
このスキームでの年金受け取りは担保なので借金と考えられ、非課税になるのがメリットと言えるだろう。
非課税で将来的に資金(年金)を引き出せるようになっている。
現役時代はもしもの時の為に、将来的には年金プランとして活用できるツープラトンの商品となっている。
また、契約当初の解約返戻金率の低い(資産圧縮率が高い)段階で個人へ譲渡する事による損金算入もやれない事はない。
生命保険の契約には保険業法が絡むのだが、貯蓄型保険商品であれば、以下コンテンツのようなプランがある。

この商品は生命保険としての機能は薄く、貯蓄性に特化した商品となっている。
活用の仕方は様々だが、経営者(理事長)のもしもの時の為の保障や退職金の構築などが行える。
この商品も法人から個人へ譲渡する事による損金算入がやれない事はない。
⇒ ご質問やご相談等はこちらから。
医療法人が行える相続対策とは?
先ほど例に出した生命保険や貯蓄性保険商品を契約することで相続対策にもなる。
法人から個人への名義変更を行う事で損金算入が可能と書いたが、その名義変更をご自身でなくお子さんやお孫さんにする事で法人から個人への資産承継が行えるからだ。
また、保険証券の名義変更をするのではなく、同じように解約返戻金が低い段階で法人を承継すれば、資産が圧縮された段階で法人を相続する事が可能となる。
海外の生命保険は利回りが高いのだが、今回ご紹介したプランは契約直後は解約返戻金率が低い(資産圧縮率が高い)ので、そのタイミングを活用すれば上手く相続していく事ができるのだ。
契約当初の解約返戻金率が低いとはいえ、契約後5~10年程度で解約返戻金が支払保険金が超える損益分岐点を迎え、その後は資産価値がどんどん高まっていくようになっているので、活用価値はとても高い。
⇒ ご質問やご相談等はこちらから。
海外オフショア籍の保険商品に加入する方法とは?
こうした優れた特性を持つ保険商品は、海外のオフショア金融センターと呼ばれる国や地域から発行されている。
所謂、金融立国に置かれている保険会社が提供する商品である。
こうした国や地域は小国である事が多く、金融政策で自国を成り立たせている。
その為、優れた金融商品や保険商品が組成しやすい環境となっていて、外貨獲得を目指している。
日本人や日本法人を受け入れている海外の保険会社もあるが、海外の保険会社は直接クライアントを受け入れている訳ではなく、IFA(Independent financial advisor)と呼ばれる正規代理店を介して契約からサポートまでをお世話になる事になる。
だが、海外の保険会社なので日本にその正規代理店(IFA)は存在しない。
なので、海外の保険商品に興味があれば、海外にある正規代理店に連絡する事になる。
正規代理店=IFAは現地の保険業を管理監督する機関や金融庁に登録されている会社の事を指す。
例えば香港であれば、政府直轄の「香港保険業監管局」に登録されている会社が正規代理店=IFAとなる。
契約に興味があれば、こうした機関に登録されている正規代理店に直接連絡してもらう事になるが、海外にある正規代理店と言えど、日本人スタッフがいる正規代理店もある。
そうした正規代理店の中で日本の医療法人の税務に詳しく、契約やサポート実績が豊富なところを選んでおけば、各医療法人に適したスキームを案内してくれる事だろう。
海外保険商品の正規代理店は数あれど、日本の医療法人の税務に詳しい正規代理店は数少ない。
海外の保険商品に興味があれば、先ずは正規代理店に直接連絡してもらいシミュレーションを提示してもらう事がスタートになってくる。
ご自身や法人の予算や考えを伝え、それに合ったプランやスキームをシミュレーションしてもらうと契約後のイメージもしやすいと思う。
⇒ ご質問やご相談、正規代理店(IFA)の選定でお悩みの方はこちらから。
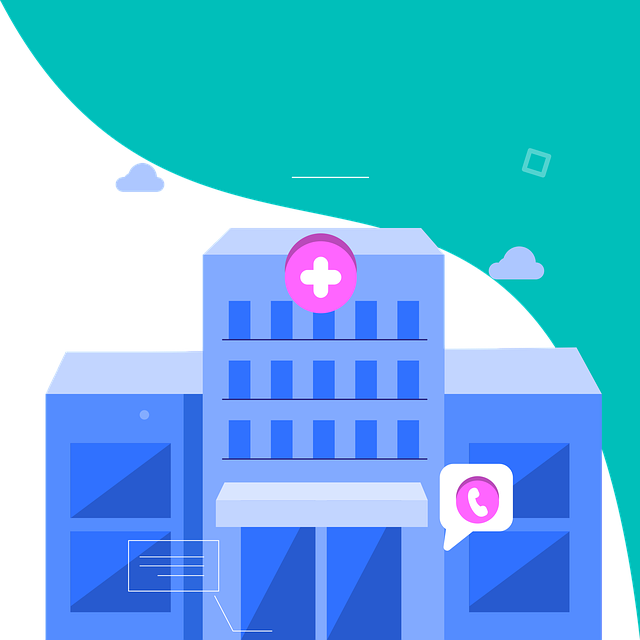


コメント