南米ベネズエラで2018年、2021年と2度に亘ってデノミネーション(略称:デノミ)が実施されている。
急激なインフレによって混乱した通貨単位を切り下げて、経済の安定化を図る事が目的のようだ。
日本でもデノミが画策されていた!通貨は分散して所持しよう!
(2018年8月)
[カラカス/バレンシア 20日 ロイター] – 南米ベネズエラは20日、通貨の単位を10万分の1に切り下げるデノミネーション(デノミ)を実施した。急激な物価上昇を抑制し、経済を押し上げる狙いがあるとみられるが、効果は疑問視されている。
マドゥロ大統領は政令でこの日を国民休日とした。このため、市内は人通りが少なく、店も閉まっているという。
大統領は17日、独自の仮想通貨ペトロにペッグした通貨制度の導入を発表。実質的には96%の切り下げとなる。さらに向こう数週間に最低賃金を3000%超引き上げ、法人税率を引き上げるほか、ガス価格を引き上げると明らかにした。
通貨ボリバルは非公式市場でこの日、1ドル=96ボリバル程度で取引されている。これは前週から実質で30%近く切り下げられた水準。ただ休日で薄商いのため相場全体を反映していない可能性があるという。
(2021年8月)
南米ベネズエラの中央銀行は5日、通貨の単位を6ケタ切り下げるデノミ(通貨単位の切り下げ)を実施すると発表した。ハイパーインフレにより、2018年にも5ケタの切り下げを行ったばかり。米国の制裁に失政や新型コロナウイルスの感染拡大も重なり、経済混乱が収束する気配はない。
過去にデノミが実施された国はベネズエラの他に北朝鮮やジンバブエといった国々が上げられる。
経済が安定しておらず、インフレーションによって通貨の価値がなくなっていくので、相対的に物価が上がってしまい単価も跳ね上がってしまう。
例えば、物価が100倍になれば100円で買えたものが10,000円になり、10,000円で買えたものが1,000,000円となる。
高額な紙幣が必要となるので、通貨単位を引き下げる事が行われるのだが、この事をデノミネーションと呼ばれている。
物価が100倍になった状態で、通貨単位を1/100に切り下げれば、これまでと同じ貨幣が使えるようになる。
見た目は同じようになるのだが、もちろんこれで経済が安定化する訳ではないだろう。
日本には関係ない事と思っているかもしれないが、日本でもデノミが画策されていた事がある。
戦前・戦後の混乱期ではなく、21世紀になってからの話だ。
小泉純一郎-竹中平蔵ラインでデノミが考えられていたのである。
(昭和21年には新円切り替えとして、インフレ対策としてデノミが実行された過去もある。)

↑過去のコンテンツ。
改めて調べてみると、福田赳夫内閣や中曽根康弘内閣の時にもデノミが検討されていたそうだ。
小泉内閣では、インフレ関係なくタンス預金を引き出したい思惑でデノミを考えていた。
政府は何か理由を付けさえすれば、こうした事が実行できてしまう。
日本のように発展した国であっても、デノミが起こったら混乱する事は間違いないだろう。
小泉内閣の時に画策されていたデノミは、表向きは海外との為替を合わせたい考えがあったようだ。
日本は主要通貨に対して100円前後や100円台のレートである事が多い。
デノミによって通貨価値を1/100に切り下げれば、為替が他国と同じようになると考えていたようだ。
こんな事をすると高齢者を中心に混乱するとの理由でデノミ案は立ち消えたが、そもそも為替を他国に合わせる事に意味があるの?と疑問に感じた人もいる事だろう。
もちろん、為替を合わせるのは表向きの理由である。
真の理由は通貨価値を下げる事によって、日本が抱える借金を減らしたい考えがあったようだ。
現在進行中の円安や物価高騰。
日本円の価値が下がっている状態だ。
たまに為替介入を実施しているが、全く力がなく直ぐに円安方向に引っ張られる。
国民には為替介入を実施する事によって政府は円安対策の仕事をしていますよ!とアピールしているのかもしれないが、実際には円安に持っていきたい考えがあると思う。
円安=日本円の価値が落ちれば、日本円の価値が下がるので、実質的に日本政府が抱えている借金額は目減りする。
また、インフレーションへの対策も同じだろう。
物価高騰=お金の価値が下がるので、実質的な借金額は目減りする。
また、物価高騰すれば消費税の税収アップになる。
円安や物価高騰(インフレーション)、実は政府の望むところなのである。
なので、デノミは実施されないとしても、今後も円安やインフレが進んでいく事を想定して、対策を練っていく必要があるはずだ。
☆ご質問やご相談等はこちらから。
円安やインフレ対策は海外で資産を持つ事!
日本国・日本円は皆さんが思っているように安心安全なものではない。
政府によっていかようにもコントロールされてしまう。
そうした状況に自分の大事な資産を侵されたくないのであれば、少なくとも余裕資金は海外の安全な場所に置いておいた方が賢明だ。
資産保全は国境を超える事が基本となる。
所謂、国際分散投資である。
気付いている人は、HSBC香港などの海外銀行口座を開設して国際資産分散を行っている。
だが、海外とは言え、銀行に資産を寝かせているよりも利回りの良い保険商品などにしていた方が資産価値は高まっていく。
例えば、サンライフ香港社が提供している貯蓄型保険商品SunJoy Globalは利回り6~7%で複利運用されている。
(商品概要は以下リンクを参照ください。)

先ず、この商品は日本にいながら契約できるスキームがある。
そして、保険料の支払いも銀行送金やクレジットカードでの引き落としに対応しているので、日本にいながらにして資産移転が完了する。
(保険料の支払いは現地窓口での現金払いも可能だが、制限あり。)
契約通貨は米ドル、カナダドル、英国ポンド、中国人民元から選べるが、米ドルにしておけば良いだろう。
海外で米ドル資産を持てるようになるのだ。
気になるリターンだが、以下のように算出されている。
◆10年目:140%
◆15年目:191%
◆20年目:279%
◆25年目:394%
◆30年目:551%
日本の保険会社では到底達成できないリターンだと思う。
日本の保険会社は日本政府に守られている一方で、低金利な日本国債を半強制的に買わされているので、利回りの良い商品を組成できない。
デノミやら円安やらインフレやらと説明し、そのヘッジが必要なのだが、純粋にこれだけの利回りが出れば資産運用商品として満足ではないだろうか?
更にこの商品は契約者・被保険者を何度も変更できるという特徴がある。
契約者は18歳以上でしかなれないが、然るべきタイミングでお子さんやお孫さんに名義変更していけば資産承継も可能となる。
証券は分割する事も可能なので、お子さんやお孫さんの人数に合わせて分割すれば、相続を巡って喧嘩になる事もないだろう。
日本円リスクを日本国内で考えても無理がある。
それは何故なら、何をしようにも日本国内では日本円を管理している日本政府の傘下になってしまうからだ。
国境を越えれば、自由度が広がるので資産保全に適した商品やスキームが見つかるのである。
そして、利回りの良い商品もあるので、インフレ対策として有用となってくる。
☆ご質問やご相談等はこちらから。
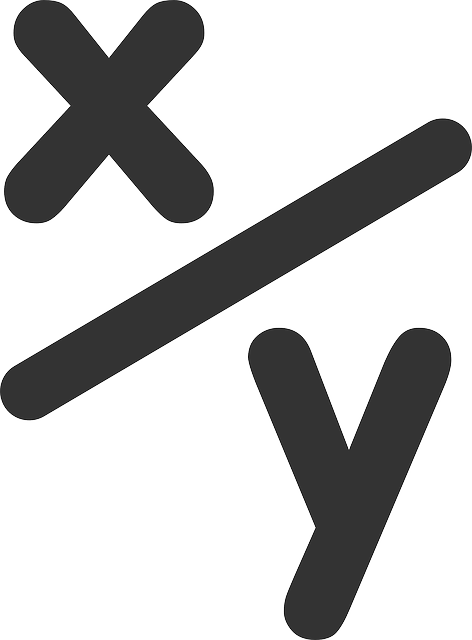


コメント